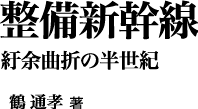全国に新幹線網を築き国土軸とすることを目指した全国新幹線鉄道整備法が施行されたのは1970年。東北・上越新幹線開業を経て次なる建設線、東北、北海道、北陸、九州(鹿児島・長崎)の5線の整備計画が決定したのは1973年のこと。しかし国鉄時代には工事着手に至らず建設凍結、JR発足後にまず北陸新幹線(長野)からようやく進み始めた。国鉄時代とJR以後は整備の方法も変わったが、常に問題は「財源」にあった。
≪東北・北海道・北陸・九州2線のきのう・きょう・あす≫
最初の長野が1997年、直近の函館が2016年で、さらに札幌、敦賀、長崎へと建設が進むが、整備計画全ての完成はいまだ見えていない。
さまざまな外的な要因にも翻弄され、複雑な歩みをたどってきた「整備新幹線5線」のドラマチックな半世紀を振り返り、建設までの動きと取り組み、開業済み各新幹線の特徴と課題を詳細にわたり解説した「整備新幹線」の決定版です。

✿本書の内容✿
【はじめに】 整備新幹線以前
(カラーページ) 整備新幹線 整備5線の現状と見どころ
第一章 全幹法と整備新幹線
❖整備新幹線建設規格の元になった山陽新幹線 ❖与党の意欲を込めた全幹法制定 ❖新幹線の定義と実現への手順 ❖手順の中に記された整備新幹線の語源 ❖整備新幹線は上下分離と公共事業化がポイント
第二章 国鉄時代の整備新幹線計画
❖整備三線と言われた東北・上越・成田 ❖現在の整備五線が基本計画に登場 ❖基本計画には十二線も登載 ❖国鉄改革〜財政悪化から国鉄改革法制定へ ❖国鉄再建監理委の答申で分割民営化へ ❖先延ばしの中で生まれた優先順位 ❖凍結の中で進められた着手への準備
第三章 財政難の中で編み出された新スキーム
❖流れは事業者負担の抑制と地方負担導入へ ❖基本スキーム決定 受益の範囲のJR負担 ❖並行在来線の経営分離 ❖新幹線鉄道保有機構の誕生
第四章 国鉄改革後の再始動
❖JR発足後 いよいよ各線事業着手へ ❖運輸省提案のミニ新幹線とスーパー特急 ❖優先順位決定で北陸が第一位に ❖既設新幹線の譲渡と鉄道整備基金 ❖公共事業化を明確にした新スキーム ❖既設新幹線譲渡収入の前倒し活用 ❖札幌・敦賀・長崎は整備線貸付料の前倒しで
第五章 整備五線それぞれのあゆみ
❖北陸新幹線 ❖東北新幹線 ❖九州新幹線鹿児島ルート ❖北海道新幹線 ❖九州新幹線西九州ルート
フリーゲージトレイン開発の経緯
第六章 各路線の特徴と現状
❖北陸新幹線高崎・長野間 ❖北陸新幹線長野・金沢間 ❖東北新幹線盛岡・新青森間 ❖九州新幹線鹿児島ルート ❖北海道新幹線新青森・新函館北斗間
建設中の整備新幹線三区間(北陸・北海道・西九州)
第七章 リニア中央新幹線
【エピローグ】 整備五線以後
(関連資料)
整備新幹線の取扱いについて(平成八年政府与党合意)
整備新幹線の手続き状況
整備新幹線関連のうごき(年表)
〔※リニア中央新幹線は「整備新幹線」には含まれませんが、建設が進められていることから、参考として経緯を収録しました〕
写真:久保田敦/塩塚陽介/山井美希/マシマ・レイルウェイ・ピクチャーズ/レイルマンフォトオフィス/鉄道ジャーナル編集部
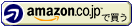 | | 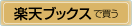 | | 
✿著者紹介✿
鶴 通孝(つる・みちたか) 1960年東京都生まれ。城西大学卒業。編集プロダクション勤務を経て1989年、鉄道ジャーナル社入社。編集業務の傍ら事業者から現場まで幅広く数多くの取材記事を担当。2017年より「鉄道ジャーナル」副編集長を務める。
| ![]()
![]()