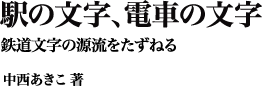日本の鉄道は明治中期に鉄道国有の方針が決まり、輸送の円滑のために車両の規格や運転の取り扱いの統一が図られた。そして、鉄道で使われる文字についても具体的な様式が決められたのである。
鉄道文字には旅客に向けたものと現場の業務用に必要なもの、その二つの流れがある。もとより職員や職人の手書きという方法に拠ったので、間違いのないよう具体的な書き方は細かく定める必要があり、文字のかたちや大きさなども今日まで規程あるいは図面による指示がなされてきた。
そのことが鉄道文字に、市中に見られる一般の様々な文字とは異なる性格を与えている。 文字を書く。文字が伝える。
鉄道文字の現場を通して携わる人の想いと技をたずねる、著者の情熱が詰まった一冊です。
  
【はじめに】 鉄道ならではの文字の奥深さ
◆ 鉄道における一枚の表示の中に、時間と人の手を経て様々な要素が凝縮し、その場に一つのメッセージとして設置され、受け手に情報が届けられる。その受け手の一人として興味の尽きない文字を眺め、それが鉄道という場においてどのように表出されてきたのか、どのような意図が込められているのかを、深く探っていきたいと思う。
✿本書の内容✿
第一章 全国に広がった国鉄書体
すみ丸ゴシックの時代
❖数十年を経て垣間見る手書き文字のインパクト
すみ丸ゴシックをたずねる/国鉄が用いた書体/電気掲示器とアクリル板/手書きの版下
【コラム】すみ丸ゴシックを書く
第二章 駅の文字にはルールがある
駅名標の決まりと移り変わり
❖百年前の駅の筆文字は教科書をお手本に書いていた
九州駅名標案内、種々見て歩き/鉄道掲示規程の変遷と駅名標/筆文字のひらがな/七枚目の駅名標/時をさかのぼる/文字を照らす/縦型の内照式電気掲示器/北国の駅に「国鉄」の風景
【コラム】駅名標で名所案内
第三章 見やすく、わかりやすく
駅名標からサインシステムへ
❖地下空間でも私たちの行動を助ける道標
営団地下鉄のゴシック4550/矢印も冒険する/大阪、地下鉄三世代の文字/阪急電鉄の丸ゴシックとロイヤルブルー
第四章 鉄道文字のもう一つの流れ
電車の文字をたずねる
❖国鉄時代の標記文字は、明治の鉄道国有当時の規程が原点
ナデとハニフ/車両の保存と標記/モハ1の復元/復元車両の手書き文字/モハ、クハ…、車両標記とは/車両標記の文字は明治時代から/転写標記の文字作業/床下の文字
第五章 車体標記が育む一体感
電車の文字のアイデンティティ
❖永年守ってきた固有の文字が職場の誇りに
名鉄電車の車両番号数字/名鉄文字のルーツを探る/番号板が育んだ「マイカー」意識/名鉄電車の番号板を作る/蒸気機関車のナンバープレート/標準書体と鷹取書体
【コラム】ラベルで伝える
第六章 文字が語る「サービスの心」
されど鉄道文字
❖現代に生きる文字、コミュニケーションツールとして
列車に乗ったら見たい文字/駅名標に見るサービスの心/文字でつながるネットワーク
 第七章 駅や電車内外で見られるさまざまな文字とサイン 第七章 駅や電車内外で見られるさまざまな文字とサイン
鉄道文字発見の楽しみ
❖およそ10年撮りためた写真と過去ログ43編で振り返る
【あとがきに代えて】鉄道文字は人との関わり
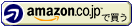 | | 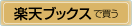 | | 
✿著者紹介✿
中西あきこ(なかにしあきこ) 1975年神奈川県生まれ。二松学舎大学大学院修了。大学時代より書道を学ぶ。雑誌連載「二駅歩き」をきっかけに地下鉄に残る旧い文字に興味を持つようになる。取材の際、国鉄時代に制定された統一書体すみ丸ゴシックと出会う。以来、手書きの駅名標文字の魅力のとりこになる。2014年より月刊『鉄道ジャーナル』で「されど鉄道文字」の連載を開始。昭和の時代感覚あふれる看板や書体をたずねてさらに取材を続けている。
 【シリーズ第一作】 【シリーズ第一作】
されど鉄道文字 −駅名標から広がる世界−
✿ かつて全国の国鉄駅に行き渡った駅名標や各種の案内掲示は、時代ごとの内部規程によって定められ、昭和35年以降、その文字書体「すみ丸ゴシック」が生まれた。この文字は職人の手書きに頼っていたことによる。機関車の番号や車両標記の文字も実は明治末年に制定された様式に準拠、基本は図面により指定される。およそ百年、駅や車両に掲げられた文字は、どのようにして書かれ、守られてきたのか。その源流をたずね、文字書体の形成と字書きの技、そして今日までの移り変わりを丹念に追った異色の鉄道書。 【詳しい内容はこちら】をご覧ください。
| ![]()
![]()